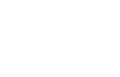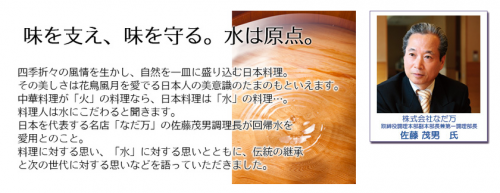
創業天保元(1830)年。
政財界はじめ各界の要人に重用され、東京サミットやG7開催の折には国賓のおもてなしをも担った「なだ万」。
そんな日本を代表する「なだ万」国内外各店での調理長を経て、現在は調理本部副本部長を務めている佐藤茂男さん。
回帰水との出会いは今を遡ること18年、平成5年の夏だったという。
水の悪さに改めて感じた水の大切さ
「品川店の調理長を拝命したのですが、当時、品川は水が悪くてね。まずいんじゃない、生臭いんですよ。その水で淹れたお茶を飲んだ時、てっきり器をよく洗っていないからだと思い(笑)、スタッフに注意をしたくらいです。でも、原因は水だった。今でこそ水道水もだいぶよくなりましたが、当時はまだまだで、水が悪い地域だったんですね。このままでは自分の料理は到底できない、と。とりあえずよそから水をいただいたり買ったりしてしのぐかたわら、浄水器をモニターで試してみました。ですが、どれひとつとして気に入るものがない。とっかえひっかえ、何社試したかわかりません」
そんな折に出会ったのが回帰水。
「どうせ、まただめだろう」と期待していなかったものの、紹介者の申し出で実験してみることに。7〜8社の水を同時に比較したところ、「一番おいしかったし、これならいける!と」。
科学的データはともかく、自分の舌で納得することが第一と、回帰水を使うことを決心。とはいえ、個人の店舗ではないため勝手には購入を決められない。
そこでまず自宅に生水器MB—500を取り付け、その水を「週に2〜3回、車で運んで使っていました」
そんな日が4年ほど続いた時、赤坂に『ジパング』という新業態店のオープンが決定、調理長に任命される。
店舗はホテルの1フロア。ホールや個室のほか寿司、鉄板焼き、おでんなどのコーナーもあり、それぞれの場で調理を行うようになっている。
「新規開店の場合は、オープン用の設備経費も認められます。そこで今度は!と思って」メインの調理場はじめ各コーナーにも、シンク下用取り付けタイプのMAX2000を6台導入。
以来、現在も使われている。

料理という舞台の陰の主役は「水」
味つけは調味料でするものではない——。
意外に聞こえるが、これが和食の基本と言う佐藤さん。
「料理は素材が持っているうまみを楽しむもの。調味料を食べるのではありません」
素材がよければ、調味料は最小限でいい。その素材のうまみを引き出すのが、出汁(だし)。だからこそ料理人はいい水、いい昆布、いい鰹節、そして素材選びにこだわるという。
たとえば、春が旬のたけのこ。朝掘りの新鮮なものをいい出汁で煮て、薄い味つけで仕上げれば…「たけのこ本来の味が出てきて、おいしくなります。
それを、たけのこの香りが残せないほど調味料で味をつけてしまうのは、いかがなものかと。素材が本来持っている味をいかに引き出し、そこにどう付加価値をつけていくか……それがわれわれプロの仕事だと思っています」
原石である素材を輝かせる、その要となるのが水。
「水が悪ければ、どんなに高級な昆布や鰹節を使っても、いい出汁はとれません。酒を入れて臭いを消したり、いろいろと方法はありますよ。でも、それは邪道でしょう」
だから当然のこと、料理人は水にこだわり、それぞれに自分の味を生かせる「水」を持っている。「私にとっては、それが回帰水だった、ということです。たかが水、されど水。残念ながら、水は決して料理の主役にはなれません。たとえば高価な食材を使えば、その原価は料理の価格に反映させることができますし、お客様にも納得していだだけます。ところが、水の場合はそうはいきません。いくらいい水を使っているからといって、料理の値段を上げることはありえません。経営ということを考えると、それがつらいところです。しかし、なくてはならない、いわば陰の立役者。あだやおろそかにはできません。私は料理は水、だと思っています」
基本あってのアレンジ伝統と革新の兼ね合いは永遠の課題
日々研究を重ね切磋琢磨してきた味も、食生活の変化に伴い少しずつ変化しているという。
「和食のみが常食であった昭和初期までにお生まれの方も、どんどん減ってきています。今60代の方々は、物心のついた頃から和洋折衷の食に触れてきた世代です。おふくろの味、家庭の味も変化してきていて当然でしょう。旬を大切にすると同時に、五節句など祭事にちなんだものが多いのも和食の特徴ですが、家庭での催しも減って、おせち料理にしても、由来や料理一つ一つの意味合いなどをご存じないことだって多い。それはいい悪いではなく、社会の流れですから仕方のないことなんです。ただ、食は文化ですから、日本人である以上、和食の火は消しちゃいけない、という気概を常に持って、調理に臨んでいます」
とはいえ、ビジネスである以上、お客様のニーズは最重要課題。
企業のトップや外国人客が多いといった店舗の立地もあり、新感覚の料理の提供はもとより、ベーシックなものにも微妙な味の変化が求められる。ただ、長い目で見ていると、奇をてらったものは飽きられるのも早く、最終的には基本の味に戻るという。
「シンプルなもの、素直なものが一番、ということでしょうか。また、お店で出すことは少ないですが、肉じゃが、筑前煮といった、名前を聞くだけで味が見える料理も大切ですね。若い頃は不本意でしたが、今となっては、なぜそうなのかよくわかります。一方、厳選した素材を手間ひまかけて丁寧に仕上げても、あまり注文がなかったりすることもあります。皮肉なものですね、料理人としては少しがっかりしますけれど……」
しかしながら、オーダーが少ないからといってお品書きから外すことはない。
ビジネス面だけを考えるとマイナスだが、「なだ万」は国内だけでも二十数店舗を擁するスケール。
将来を見据えた次世代の育成も、老舗企業としての使命である。
「和食の背景や基本を理解し、調理できるよう、毎月テーマを決めて、何がしかの技術や伝統を継承していくべく務めています」
伝統的な技法や味など、『本物』を会得した後でアレンジを加え、自分なりにオリジナリティを出すのはかまわない、と佐藤さん。しかし、「味は形のないものだから、どうにでもなる。だからこそ、基本がしっかりしていなくては。料理人が基本を学ばずめいめい勝手なことをしていては、日本の味も伝統も失われてしまうと思いますね」
そんな佐藤さんの目指す究極の味は
「シンプルななかに奥行きがあり、メリハリが利いていて記憶に残る味」
コースで食べて3日後、5日後に記憶に残る味が1〜2品あれば、十分だという。さらに、100人のお客様に料理をお出ししても、100人すべてを満足させることはできない。90人の方が美味しいといってくださればそれでよい、とも。言葉の端々から、料理に対する情熱と自信に加え、佐藤さんの謙虚な人柄が伝わってくる。
「今や便利さの追求が進みすぎ、一年中なんでも手に入ります。たとえばトマトやきゅうりなど、品種改良やハウス栽培の結果、通年で食べられるようになりました。日本人の勤勉さのたまものでしょう。反面、旬の感覚がなくなり、本来の味も失われつつあります。今後どうあるべきなのかと考えていた矢先に、今回の大震災。被災者の皆様は大変お気の毒でことばもありませんが、これを機に、さまざまなことが見直されてきていますね。好むと好まざるとにかかわらず、すべてのテンポが少し緩やかになり、便利さの追求にも歯止めがかかるのではないか、そして自然本来のあり方に添った生き方が見直されるようになるのでは、と思います。これは広い意味での自然回帰ということではないでしょうか。自然の恵みに感謝し、自然に畏敬の念を持つべきなのは和食の世界も同じこと。これからも、時代の変化にも対応しつつ、伝統のよさを守って次の世代に日本の味と文化を伝えていきたいと思っています」